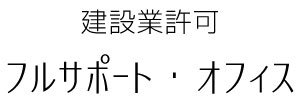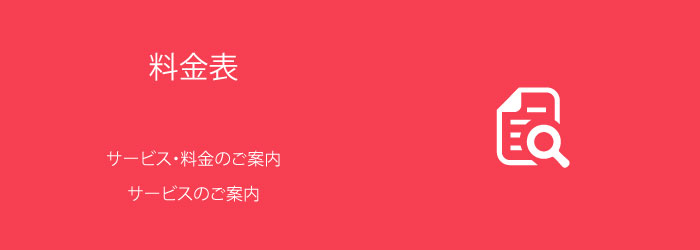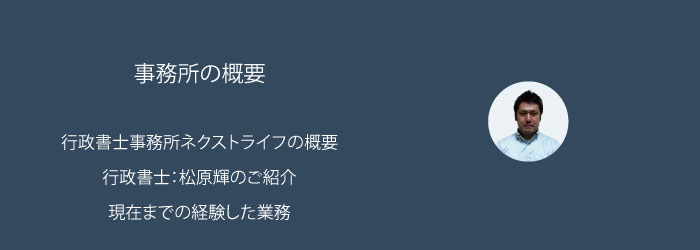Contents
建設業の経営の経験がポイントになります

許可を受けようとする建設業について、 建設工事の施工に必要とされる資金調達・技術者配置・契約締結など経営についての経験 を持っている方(すなわち「経営業務を管理する責任者」)を「経営業務の管理責任者(経管)」として建設業許可を申請する際には常勤させなければいけません。
経管の要件
「経営業務の管理責任者」は、建設業の経営経験があれば誰でもなれるわけではありません。
下記の要件を満たさなければ経営業務の管理責任者として建設業許可申請をすることができず、許可取得後に経管がかけた場合等は許可取り消しとなります。
➁一定の年数の建設業の経営経験があること
個人では「個人事業主等」
法人では「常勤の役員」であること
上記のとおり「経営業務を管理する責任者」が経営業務の管理責任者となります。
責任者でなければならないので、個人事業であれあ「個人事業主」または「登記した支配人」、法人であれば常勤の役員(取締役等)でなくてはなりません。
登記した支配人について
常勤の役員について
一定の年数の建設業の経営経験があること
上記の責任者は、自社において指定したものが就くことができるわけではなく、一定の経営経験が必要おになります。
具体的には下記の4パターンとおりです。
➀許可を受けようとする建設業許可について
5年以上の経管としての経験
例えば、「とび・土工工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者としての経験を「とび・土工・コンクリート」を内容とする工事についての経管としての経験がなくてはなりません。それ以外の場合には下記にある「経管として7年以上」となります。
➁許可を受けようとする建設業許可以外の建設業について
7年以上の経管としての経験
許可を受けようとする建設業許可の経管としての経験が足りない場合は、表題のとおり7年以上他の建設業の経管としての経験があれば大丈夫です。
➂許可を受けようとする建設業について経管に準ずる地位にあって
一定の経験を有する者
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは使用者が法人である場合には「役員に次ぐ職制上の地位」、個人である場合には「個人に次ぐ職制上の地位」のことを言います。年数は下記のとおり2パターンあります。
➃国土交通大臣が建設業法第7条第1号イに掲げるものと
同等以上の能力を有すると認める者
「建設業法第7条第1号イ」とは上記の「許可を受けようとする建設業許可について5年以上の経管としての経験」のことを言います。
上記において現実性のあるものは、➀➁ではないでしょうか。➂については法人で取締役会設置会社でなければならない前提があったり、➃は国土交通大臣が同等と認める者という不明瞭な内容です。
ポイント
上記に記載している内容は基本となります。
ここで上記を踏まえ注意したいこと・ポイントとなることを下記にご案内します。
経管になれない者
経管としての経験を積んできていても、経営業務の管理責任者になれない者も中にはいます。
下記に該当しないように日頃から注意しなければなりません。
➁他の会社の代表取締役等(常勤ではないため)
➂他社の技術者となっている場合
➃国会議員・地方公共団体の議員(常勤できないため)
上記は例外があります。
➁については他の会社において代表取締役が複数存在するため、申請する法人において常勤性に問題がない場合は経管としての申請が可能です。➂については他法令により専任が必要な者である場合(管理建築士・宅地建物取引免許における専任の取引士等)は経管になることはできませんが、この場合同じ営業所において専任する場合であれば経管としての申請が可能となります。
「常勤」について
経営業務の管理責任者は「常勤」でなくてはなりません。常勤でなければ建設業許可を取得することはできませんし、取得後も経管が常勤でなくなれば要件を満たさなくなることを意味しますので、建設業許可が失効してしまいます。「常勤」の意味は、常にその事業にいること・・・と何となくイメージはつきますが具体的にしておいたほうが建設業許可を取得し、維持するためにも大切です。常勤については「建設業許可事務ガイドライン」にて説明されており、「原則として本社、本店頭において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事しているものがこれに該当する」と常勤であるものの態様が記載されています。
「経管」一つとっても建設業許可は複雑です
ここまで経営業務の管理責任者についてご案内してきましたがいかがでしたでしょうか?
建設業許可の大きな要件である「5つの要件」は、それぞれにおいて更に複雑なルールがあるわけです。経営業務の管理責任者も例外ではありません。もし上記の要件に該当せず経管がいない・・・そんなときはいつでも行政書士事務所ネクストライフにご相談ください。一緒に経管について作戦を立てましょう。弊所にご相談くださることでわかりづらいこと・気づかなかったことを明確にしていきましょう。